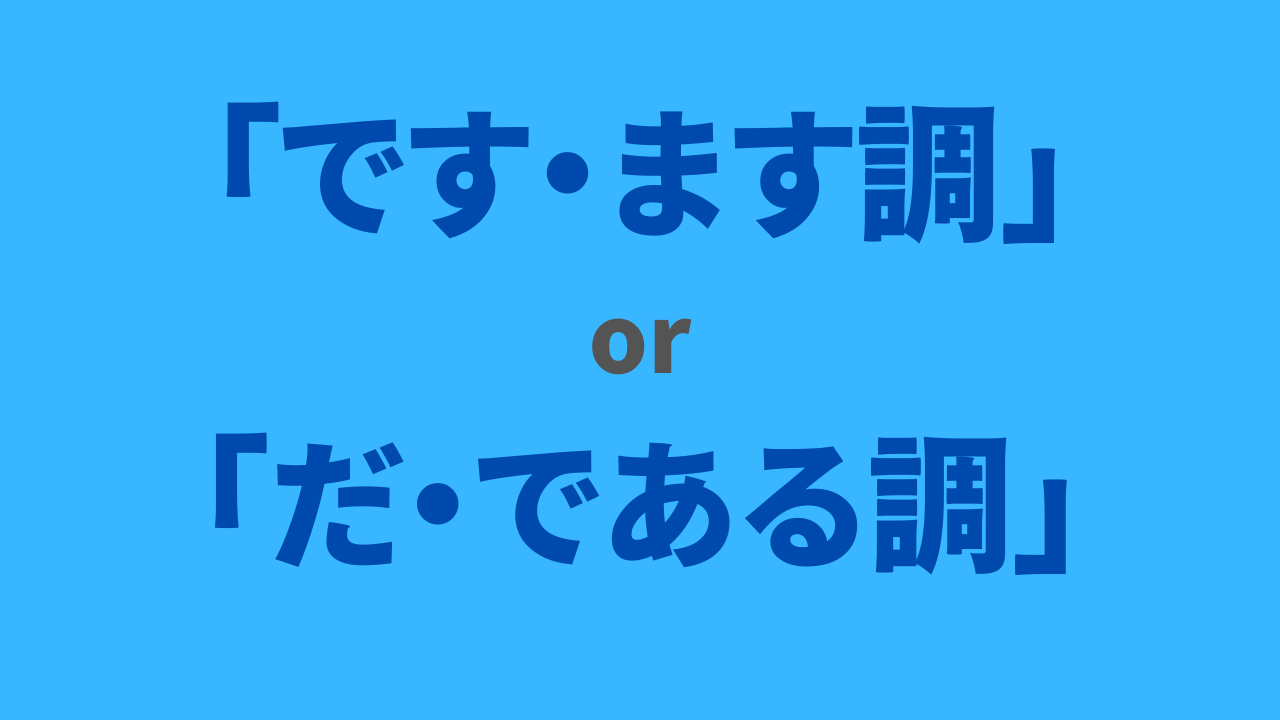- 「です・ます調」「だ・である調」の違いは?
- Webライティングでは「です・ます調」「だ・である調」どちらを使えばいいの?
- どちらの語尾を使えば、読者に響く文章になるの?
Webライティングにおいて、読者に与える印象を大きく左右するのが、「です・ます調」と「だ・である調」の使い分けです。
どちらを選ぶかによって、記事の雰囲気や信頼性、読者との距離感が全く異なります。しかし、適切な使い分けのルールを理解せず、どちらを使ったらいいか悩む方も多いのではないでしょうか。
この記事では、Webライティング初心者のあなたのために、「です・ます調」と「だ・である調」それぞれの基本的な特徴、効果的な使い分けのルールを分かりやすく解説します。
さあ、あなたの記事が、ターゲットユーザーに効果的に伝わるための語尾の使い分けをマスターしましょう!
『「です・ます調」「だ・である調」』を学ぶ前に、「書けない」という悩みを根本から解決したい、体系的にWebライティングを学びたい方は、まずこちらの記事をご覧ください。
▶︎ 「【完全保存版】書けない悩みを解決!Webライティングの教科書」

現在会社に勤めながら副業でWebライターをしています。会社では雑誌の編集を担当しており原稿を依頼する側ですが、自宅ではWebライターとして仕事を受けています。
「です・ます調」と「だ・である調」の違いとは?

「です・ます調」と「だ・である調」って何?

「です・ます調」と「だ・である調」で文末表現を使い分けることです!
「です・ます調」と「だ・である調」というのは聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。
「です・ます調」は敬体(けいたい)、「だ・である調」は常体(じょうたい)と言われます。
文体によって文章の印象は大きく変わります。特にWebライターは、その使い分けの基本ルールをしっかりと理解しておくことが大切です。
それぞれの特徴と基本的な違い
「です・ます調」と「だ・である調」は、日本語の文章における代表的な文体です。それぞれの特徴を解説します。
① 「です・ます調」
- 読みやすく、親しみやすい印象を与える
- 日常会話に近い語り口調
- 一般の読者向けの文章やブログ記事、説明文に適している
② 「だ・である調」
- 断定的で、論理的・客観的な印象を与える
- 事実や意見をはっきりと伝える
- 論文、ビジネス文書、専門記事などに適している
つまり、「です・ます調」は一般の読者向けのやわらかく親しみやすい文章に、「だ・である調」は客観的で論理的な文章に適しています。
日本語における文体の歴史的背景
日本語の文章は時代によって使われ方が変化してきました。昔の文書は「である」調が主流でしたが、近年では「です・ます調」が多く使われるようになっています。
特に、Webサイトの文章やSNSでは、読者との距離を縮めるために「です・ます調」がよく使われています。
一方で、論文やビジネス文書では、今なお「だ・である調」が主流です。なぜなら、客観的な情報を伝える必要があるため、親しみやすさは重視されないからです。
「です・ます調」と「だ・である調」の使い分け方法
「です・ます調」と「だ・である調」、どちらを使えばいいのか?使い分け方法・使うべきケースを解説します。
1~4の順で解説しますのでご覧ください!
- 読者層に合わせた適切な文体の選び方
- 文章の目的に応じた適切な文体の選び方
- 「です・ます調」を使うべきケース
- 「だ・である調」を使うべきケース
読者層に合わせた適切な文体の選び方
文章を書くときには、まず 「誰に向けた文章なのか」 を考えましょう。誰に向けた文章かが決まると、自ずと「です・ます調」「だ・である調」どちらの文体が良いかが決まります。
例えば、一般の読者や初心者向けは、「です・ます調」の方が親しみやすく伝わりやすくなります。
一方、専門家やビジネス層向けは、「だ・である調」の方が論理的・客観的で信頼感がアップします。
| 読者層 | 適した文体 |
|---|---|
| 一般読者・初心者・若者向け | です・ます調(親しみやすさ重視) |
| 専門家・ビジネス層 | だ・である調(論理的・客観的) |
文章の目的に応じた適切な文体の選び方
文章の目的が何なのかも考慮して、最適な文体を選びましょう。ブログの記事で読者に情報を分かりやすく伝えたい場合には、「です・ます調」が適しています。
大学などの学術論文やビジネスの報告書など、論理的・客観的で説得力を持たせたい場合には「だ・である調」が適しています。
| 文章の目的 | 適した文体 |
|---|---|
| 情報を分かりやすく伝えたい (ブログ記事) | です・ます調 |
| 論理的・客観的で説得力を持たせたい (論文・報告書) | だ・である調 |
このように、 文章の目的を考慮して文体を選ぶ ことが重要です。
「です・ます調」を使うべきケース
「です・ます調」は、読者に 親しみやすさ を感じてもらいたいときに適しています。ブログ記事や初心者向けの解説記事では、「です・ます調」を使うことで 分かりやすさ が向上します。
また、SEOの観点でも、「です・ます調」の方が滞在時間が長くなる傾向があります。
これは、読者が記事を分かりやすいと感じるため、最後まで読んでもらいやすいためです。
【です・ます調】がオススメ!
- 初心者向けの説明記事
- 読者との距離を縮めたいブログ記事
- 会話調で進めるコンテンツ
以下の文章を比べてみましょう。
<例文比較>
①「です・ます調」
「文章を書くとき、どの文体を選ぶか迷いますよね? この記事では、「です・ます調」と「だ・である調」の違いを解説します。」
②「だ・である調」
「文章を書く際、どの文体を選択すべきか迷うことがある。本記事では、「です・ます調」と「だ・である調」の違いを解説する。」
➡ ①「です・ます調」の方が 親しみやすく、話しかけるような印象 になります。
「だ・である調」を使うべきケース
「だ・である調」は、論理的・客観的な文章を書くときに適しています。例えば、以下のような場合に適用されます。
【だ・である調】がオススメ!!
- 研究論文や専門的な記事
- ビジネスレポートや企画書
- ニュース記事や評論
<例文比較>
①「です・ます調」
「このデータを見ると、売上が伸びていることがわかります。」
②「だ・である調」
「このデータを見ると、売上が伸びていることが明らかである。」
➡ ②「だ・である調」の方が、 事実を論理的に伝える印象 になります。
ビジネスの場では「である」調の方が権威性を持ちやすいため、フォーマルな文章ではこちらが好まれます。
「です・ます調」と「だ・である調」を混ぜるのはNG?
「です・ます調」と「だ・である調」を混ぜてもいいのでしょうか?基本的には混ぜないようにしましょう。
1~2の順で解説しますのでご覧ください!
- 混在させるデメリット
- 例外的に許容されるケースと工夫の仕方
混在させるデメリット
「です・ます調」と「だ・である調」を同じ文章内で混ぜていいのでしょうか? 基本的に混ぜるのは止めましょう。
混在させることで以下のようなデメリットが生じます。
| ①読みにくい | 文章が読みにくくなり、読者が途中で離脱する可能性が高くなります。 |
| ②一貫性がない | 文章の一貫性がなくなり、違和感を与えます。 例:「この商品はとても便利です。さらに、耐久性にも優れている。」 |
| ③信頼性が低下 | 文体が統一されていないと、まとまりのない印象 になり、読者に不信感を与えます。 |
| ④リズムが崩れる | 「文章のリズム」が崩れるため、読者にとって読みづらくなります。 |
例外的に許容されるケースと工夫の仕方
文体の統一が絶対ではなく、 意図的に混ぜることが許容される場合 もあります。
- 会話文では両方の文体が自然に混ざることがある
- 例:「この機能はすごく便利です。なぜなら、最新技術が使われているからである。」
- 特定の部分だけ強調したい場合
- 例:「この製品は、初心者でも簡単に使えます。しかし、耐久性には課題があるといえる。」
➡ 意図的に混ぜる場合は、 見出しや改行を活用し違和感を最小限に抑える工夫が必要です。
SEOライティングにおける文体の影響とは?
SEOライティングにおいて、文体はどのように影響するのでしょうか?
1~2の順で解説しますのでご覧ください!
- 検索エンジンは文体をどのように評価するか?
- 読者の滞在時間と離脱率を左右する要因
検索エンジンは文体をどのように評価するか?
Googleの検索アルゴリズムは、 文章の文体(です・ます調 or だ・である調)を直接評価するわけではありません。しかし、 読者の満足度 を重視するため、文体の選び方が間接的にSEOに影響を与えることがあります。
例えば、以下の要素が重要です。
| ①SNSでの拡散 | 「です・ます調」の記事は、SNSなどでシェアされやすい。 |
| ②読者の滞在時間 | 読みやすい文体の方が、読者が長く記事を読んでくれます。 → SEO評価が向上 |
| ③離脱率 | 文体が統一されていないと、読者がすぐにページを離れてしまいます。→ SEO評価が低下 |
読者の滞在時間と離脱率を左右する要因
文体選びが、読者の行動に大きな影響を与えます。文体によって読者の滞在時間にも影響し、読みづらいと離脱につながります。
- 一般読者向け記事 ➡ 「です・ます調」で読みやすさ重視
- 専門家向け記事 ➡「だ・である調」で信頼性重視
また、 文章が長くなるほど、文体の統一が重要 になります。SEO対策を考えるなら、 統一した文体で最後まで読んでもらえる記事作りを意識しましょう。
まとめ
この記事では、「です・ます調」と「だ・である調」それぞれの特徴と、Webライティングにおける使い分けの基本ルールを解説してきました。
重要なのは、記事の目的、想定読者、サイト全体のトンマナ(トーン&マナー)に合わせて、どちらか一方に統一することです。
一般的に、読者に寄り添う親しみやすさを重視するなら「です・ます調」が、客観性や専門性、権威性を強調するなら「だ・である調」が適しています。
SEOの面では、どちらの語尾が直接的に有利不利ということはありません。しかし、読者の離脱を防ぎ、記事を最後まで読んでもらうためには、読者層に合った語尾を選ぶことが非常に重要です。
今回学んだ語尾の使い分けを意識することで、あなたの記事は、よりターゲットユーザーの心に響き、伝わるようになるでしょう。
ぜひ、今後のライティングに生かして、読者から信頼される文章を書いていきましょう。
なお、「書けない」という悩みを根本から解決したい、体系的にWebライティングを学びたい方は、まずこちらの記事をご覧ください。
▶︎ 「【完全保存版】書けない悩みを解決!Webライティングの教科書」