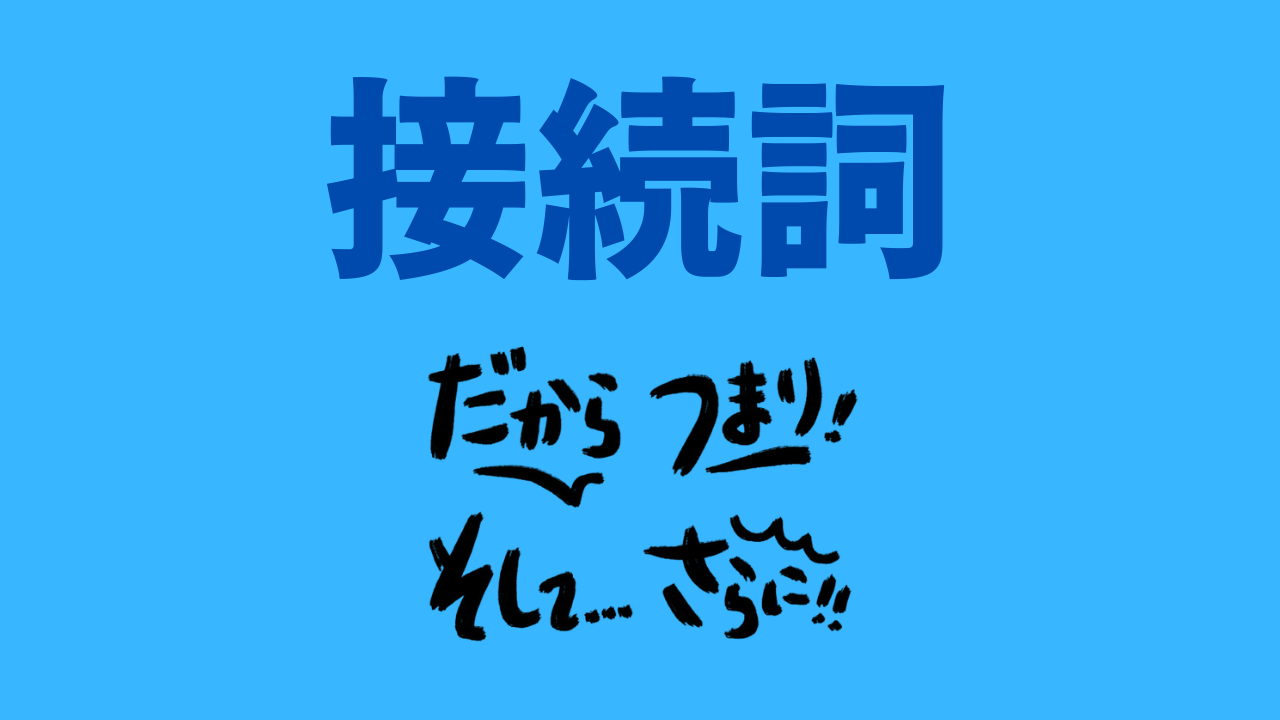- 文章がなんだか単調になってしまう
- なんとなく読みづらい
- 言いたいことがうまくつながらない
と感じたことはありませんか?そのお悩み、もしかしたら接続詞が解決してくれるかもしれません。
接続詞は品詞の一つで、文と文をつなぐ役割を持っており、「そして」「しかし」「だから」などが代表例です。
「つなぎ言葉」と言われ一見地味な存在ですが、接続詞を適切に使うことで文章の流れがスムーズになります。読者にとって読みやすく、伝わりやすい文章に変わるのです。
本記事では、接続詞の種類やそれぞれの使い方、誤用しやすいポイント、そして実践的な使い分けのコツまでを解説します。
文章力をワンランクアップさせたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
接続詞を学ぶ前に、「書けない」という悩みを根本から解決したい、体系的にWebライティングを学びたい方は、まずこちらの記事をご覧ください。
▶︎ 「【完全保存版】書けない悩みを解決!Webライティングの教科書」

現在会社に勤めながら副業でWebライターをしています。会社では雑誌の編集を担当しており原稿を依頼する側ですが、自宅ではWebライターとして仕事を受けています。
接続詞とは?種類と意味を理解しよう

接続詞って何ですか?

接続詞とは、文と文をつなぎ意味を分かりやすくする言葉です。
接続詞とは、文と文をつなぎ文章全体の意味、関係性を分かりやすく示す言葉です。文章の中で、接続詞は情報を整理し、読者に内容を分かりやすく手助けしてくれます。
ここでは、接続詞の主な種類とそれぞれの意味を詳しく解説します。
1~の順で解説しますのでご覧ください!
- 接続詞とは?文と文をつなぐ品詞の一つ
- 接続詞の主な種類とそれぞれの意味
- 【一覧表付き】Webライティングに役立つ接続詞の意味と使い方まとめ
接続詞とは?文と文をつなぐ品詞の一つ
接続詞とは、文と文をつないで文章の流れを作り出してくれる品詞の一つで、自立語です。接続詞が話の方向性を示してくれるため、分かりやすく読みやすい文章へと変えてくれます。
Webライティングにおいては、読者の理解を助け、飽きさせない文章構成のために接続詞は欠かせません。
接続詞の主な種類とそれぞれの意味
接続詞は、その役割と意味合いによっていくつかの種類に分けられます。それぞれの特徴を理解したうえで、文章の内容に合った接続詞を適切に使い分けることが重要です。
順接(じゅんせつ)
順接の接続詞とは、前の文章の内容を原因・理由として、当然の結果がうしろの文章に続く場合わに使われます。「だから、したがって、そのため、それで、そこで、すると」などがあります。
| だから | 前の事柄が原因や理由となり、後の事柄が結果として導かれることを示します。 (例:一生懸命努力した。だから、有名なWebライターになった。) |
| したがって | 前の事柄から論理的な結論や判断が導かれることを示します。 (例:データに基づいた分析を行った。したがって、この推計は妥当と言える。) |
| そのため | 前の事柄が原因や理由となり、後の事柄が起こることを示します。 (例:原稿の納品が遅れた。そのため、掲載に間に合わなかった。) |
| ゆえに | やや硬い表現で、前の事柄が理由となり、後の事柄が結論として導かれることを示します。(例:彼は努力を怠らなかった。ゆえに、大成功を収めた。) |
| すると | 前の動作や状況に続いて、次の動作や状況が起こることを示します。 (例:Webライターの勉強を続けた。すると、徐々にライティングがうまくなった。) |
逆接(ぎゃくせつ)
逆接の接続詞とは、前の文や段落の内容とは反対のことや、予想外の結果を示す際に使われます。「しかし、だが、けれども、ところが」などがあります。
| しかし | 前の内容とは異なる事柄を示す、最も一般的な逆接の接続詞です。 (例:ブログは始めるのは簡単です。しかし、稼ぐのは難しい。) |
| だが | やや硬い表現で、前の内容とは異なる事柄を示します。 (例:彼は才能がある選手だ。だが、怪我が多い。) |
| けれども | やや柔らかい印象を与える逆接の接続詞です。 (例:このレストランは美味しい。けれども、少し値段が高い。) |
| ところが | 前の状況から予期しない事態が起こることを示します。 (例:計画は順調だった。ところが、急なトラブルが発生した。) |
並列・添加(へいれつ・てんか)
並列・添加の接続詞は、複数の事柄を対等な関係で繋いだり、情報を付け加えたりする際に使われます。「そして、また、さらに、なお」などがあります。
| そして | 時間的、論理的に順序のある事柄を繋いだり、単に事柄を並列したりする際に使われます。 (例:キーワードを調べ、そして、ブログ記事を書いた。) |
| また | 同様の事柄を付け加える際に使われます。 (例:彼は書くのが上手い。また、話すのも得意だ。) |
| さらに | ある事柄に加えて、程度や範囲がより進んだ事柄を付け加える際に使われます。 (例:記事の品質が良い。さらに、納品も早い。) |
| 加えて | ある事柄に別の事柄を付け足す際に使われます。 (例:ブログ記事の内容が優れている。加えて、デザインも洗練されている。) |
| あるいは | 複数の選択肢を示す際に使われます。 (例:コーヒーあるいはカフェラテはいかがですか?) |
対比・選択(たいひ・せんたく)
対比・選択の接続詞は、二つ以上の事柄から一つを選んだり、可能性を示したりする際に使われます。「または、あるいは、もしくは」などがあります。
| または | 二つ以上の事柄の中からいずれか一つを選ぶことを示します。 (例:インスタまたはブログを始めようかな。) |
| あるいは | 「または」とほぼ同様の意味で使われますが、やや文語的(書き言葉)な印象を与えます。 (例:賛成あるいは反対の意見を述べてください。) |
| もしくは | 「または」よりもさらに限定的な選択肢を示すことがあります。 (例:ブログのトップページは、A案もしくはB案から選ぼう。) |
説明・補足(せつめい・ほそく)
説明・補足の接続詞は、前の文や段落の内容をより詳しく説明したり、補足情報を加えたりする際に使われます。「なぜなら、つまり、すなわち、たとえば」などがあります。
| なぜなら | 前の事柄の理由や原因を示す際に使われます。 (例:彼はWebライターとして独立した。なぜなら、ライティングで稼ぐ自信があるからだ。) |
| つまり | 前の内容を別の言葉で言い換えたり、要約したりする際に使われます。 (例:彼はWebライターをまとめる力があり。つまり、彼がディレクターに向いている。) |
| たとえば | 具体的な例を挙げて説明する際に使われます。 (例:さまざまな趣味を持っている。たとえば、サッカーや野球が好きだ。) |
| 要するに | 前の内容を簡潔にまとめる際に使われます。 (例:ライティングについて説明しましたが、要するに、AIに全てを頼ってはいけない。) |
転換(てんかん)
転換の接続詞は、文章の中で話題を変えたり、視点を移したりする際に使われます。「さて、ところで、ちなみに」などがあります。
| さて | 新しい話題を始める際に使われます。 (例:さて、次にブログテーマを考えよう。) |
| ところで | 前の話題から少し離れた別の話題を始める際に使われます。 (例:今回の記事はとても良いですね。ところで、次の執筆予定は?) |
| ちなみに | 前の話題に関連する補足情報を提供する際に使われます。 (例:このWebライターは優れている。ちなみに、私の会社の社員だ。) |
| それでは | 前の話を受けて、次の行動や話題に移る際に使われます。 (例:説明は終わった。それでは、質疑しよう。) |
【一覧表付き】Webライティングに役立つ接続詞の意味と使い方まとめ
| 接続詞 の種類 | 主な接続詞 | 意味と主な使い方 |
|---|---|---|
| 順接 | だから、したがって、そのため、ゆえに、すると、それで、そこで、その結果 | 前の内容を受けて、結果や理由、自然な流れを示す |
| 逆接 | しかし、しかしながら、だが、けれども、それなのに、ところが、にもかかわらず、とはいうものの、とはいえ、それでも | 前の内容と反対のことや、予想外の結果を示す |
| 並列・添加 | そして、また、さらに、加えて、それから、および | 複数の事柄を対等な関係で繋いだり、情報を付け加えたりする |
| 対比・選択 | または、あるいは、もしくは、それとも、むしろ、 | 二つ以上の事柄から一つを選んだり、可能性を示したりする |
| 説明・補足 | なぜなら、つまり、たとえば、要するに、ただし、もっとも | 前の内容を詳しく説明したり、補足情報を加えたりする |
| 転換 | さて、ところで、ちなみに、それでは、では、次に | 話題を変えたり、視点を移したりする |
Webライターが実践すべき接続詞の使い方
Webライターとして、読者に分かりやすく情報を伝えるためには、接続詞を効果的に使う必要があります。ここでは、具体的な例文を比較しながら、接続詞の選び方や使い方のポイントを解説します。
接続詞一つで印象が変わる!具体的な例文で比較
接続詞の有無や選び方によって、文章の印象は大きく変わります。以下の例文でその違いを見てみましょう。
①(悪い例)接続詞がない場合
この車は日本車です。価格も手頃です。多くの人に人気があります。
⇒ この文章は、それぞれの文がぶつ切りのため情報のつながりが曖昧です。そのため読者は、日本車であることと、価格が手頃なため人気に関係があることなどを推測する必要があります。
文章全体が単調で流れが悪く、言いたいことが分かりにくい印象を与えます。
②(良い例)適切な接続詞を使った場合
この車は日本車です。その上、価格も手頃です。そのため、多くの人に人気があります。
⇒ 「その上」と「そのため」という接続詞を使うことで、製品が日本製で手頃な価格が人気の理由であることが明確に伝わります。
文章の流れがスムーズになり、読者は内容を容易に理解できます。
読者に伝わる!接続詞を選ぶ際のポイント
読者に分かりやすい文章を書くためには、接続詞を選ぶ際に以下の三つのポイントを意識しましょう。
文脈を正確に捉える:前後の文の意味関係を意識する
接続詞を選ぶ際は、前後の文がどのような意味関係にあるかを正確に捉える必要があります。順接、逆接、並列など、文脈に合った接続詞を選ぶことで、文章の論理的な繋がりが明確になります。
意味関係を誤ると、読者に誤解を与えたり、分かりづらくなったりする可能性があるので注意しましょう。
同じ接続詞の連続を避ける:文章のリズムを意識する
同じ接続詞を繰り返して使うと、文章が単調になり読者は飽きてしまいます。同じ語尾も繰り返さない方がいいと言われますが、接続詞も同じです。
例えば逆説の接続詞の場合「しかし」ばかりを使うのではなく、「だが」「けれども」なども使いましょう。同じ逆接の意味を持つ接続詞を使い分けることで、文章にリズムが生まれ、読みやすくなります。
Webライティングで差がつく!接続詞の効果的な使い方
Webライティングにおいては、接続詞を効果的に使うことで、文章の表現力と説得力を高めることができます。
①情報を整理して伝える接続詞:「まず」「次に」「そして」「最後に」
例)記事を作成する手順は4段階です。まず、キーワードを調査します。次に、競合を調査します。そして、構成を考えます。最後に記事を執筆します。
複数の情報を順序立てて説明する際に、「まず」「次に」「そして」「最後に」といった接続詞を使うことで、文章の構成が分かりやすくなり、読者は情報を整理しながら読み進めることができます。
②読み手の疑問を解消する接続詞:「なぜなら」「つまり」
例)ブログで稼ぐのは簡単ではありません。なぜなら、競合が多いからです。つまり、ブログで稼げるのは、数パーセントの人だけです。
読者が疑問に思うであろう点や、理解を深めるために必要な説明を加える際に、「なぜなら」や「つまり」といった接続詞を使うことで、親切で分かりやすい文章になります。
③段落間のつながりをスムーズにする接続詞:「一方」「これに対して」
例)多くのライターが自分のブログを開設しています。一方、TwitterなどSNSだけを使っているライターもいます。
「一方」や「これに対して」といった接続詞を使うことで、前後の文章内容が対比されていることや、新しい視点が導入されることを示すことができます。
これにより、文章全体の流れがスムーズになり、読者は内容の展開を自然に理解できます。
注意点:接続詞の誤用と改善策【より自然な文章へ】を
接続詞は文章の流れをスムーズにする強力なツールですが、誤った使い方をしてしまうと、かえって文章を分かりにくくしたり、不自然な印象を与えたりすることがあります。
ここでは、よくある接続詞の誤用例と、それを改善するための方法について解説します。
1~2の順で解説しますのでご覧ください!
- よくある接続詞の誤用例:あなたの文章は大丈夫?
- 接続詞の重複を避けるための言い換え表現
よくある接続詞の誤用例:あなたの文章は大丈夫?
接続詞をなんとなく使っていると、意図せず誤用してしまうことがあります。以下のケースに心当たりがないか、チェックしてみましょう。
意味が合わない接続詞を使ってしまうケース
最も多いのが、前後の文脈と接続詞の意味が合っていないパターンです。例えば、逆接の関係なのに順接の接続詞を使ってしまったり、理由を説明する場面で並列の接続詞を使ってしまったりするケースです。
①悪い例:意味が合わない接続詞
彼は毎日ライティングした。だから、Webライターになれなかった。
⇒ この場合、「しかし」や「にもかかわらず」など逆接の接続詞が適切です。
②良い例:意味が合う接続詞
彼は毎日ライティングした。にもかかわらず、Webライターになれなかった。
⇒ 逆接の接続詞「にもかかわらず」を入れて、改善されました。
必要のない接続詞を多用してしまうケース
「なんとなくつながっている方がいいだろう」と考えて、本来不要な場所にまで接続詞を挟んでしまうことがあります。これにより、文章が冗長になり、かえって読みにくくなります。
①悪い例:不要な接続詞を使っている
昨日は一日中家にいました。なので、ブログ記事を書いていました。
⇒ この場合、接続詞の「なので」でつなぐ必要はありません。
②良い例:不要な接続詞は使わない
昨日は一日中家にいたので、ブログ記事を書いていました。
⇒接続助詞「ので」で、 一つの文章に統合します。
接続詞の重複を避けるための言い換え表現
同じ接続詞の繰り返しは避けたいもの。そんな時は、言い換え表現を活用しましょう。
| 接続詞の例 | 言い換え表現の例 |
|---|---|
| しかし | だが、けれども、ところが、一方で、その反面 |
| だから | そのため、したがって、ゆえに、結果として、これにより |
| そして | また、加えて、さらに、その上、それから |
| つまり | 要するに、すなわち、言い換えれば、具体的には |
⇒ これらの言い換え表現を効果的に使うことで、より自然で洗練された文章に変わります。
まとめ
接続詞は、文章の流れを整え、論理的なつながりを生み出す大切な要素です。単なる「つなぎ言葉」ではなく、読者の理解を助け、リズムのある読みやすい文章をつくるために欠かせません。
本記事では、Webライターにとって不可欠な接続詞の基本や使い方を、具体例を交えて詳しく解説しました。
適切な接続詞を選ぶことで、
✔ 論理の流れがスムーズに伝わる
✔ 読者のストレスを減らし、理解を深められる
✔ 文章全体の印象が引き締まる
こうした効果が、確実にあなたのライティングに現れます。
ぜひ、今日から学んだ知識を日々の執筆に生かしてみてください。基本を理解し、実践を重ねることで、文章の説得力と魅力は格段にアップします。
接続詞を“味方”にして、読者に届く、伝わる文章を目指しましょう!
「もっと体系的にWebライティングを学びたい」「書くことに悩んでいて、具体的な解決策が欲しい」そんな方は、こちらの記事もぜひ参考にしてみてください。
▶︎ 「【完全保存版】書けない悩みを解決!Webライティングの教科書」