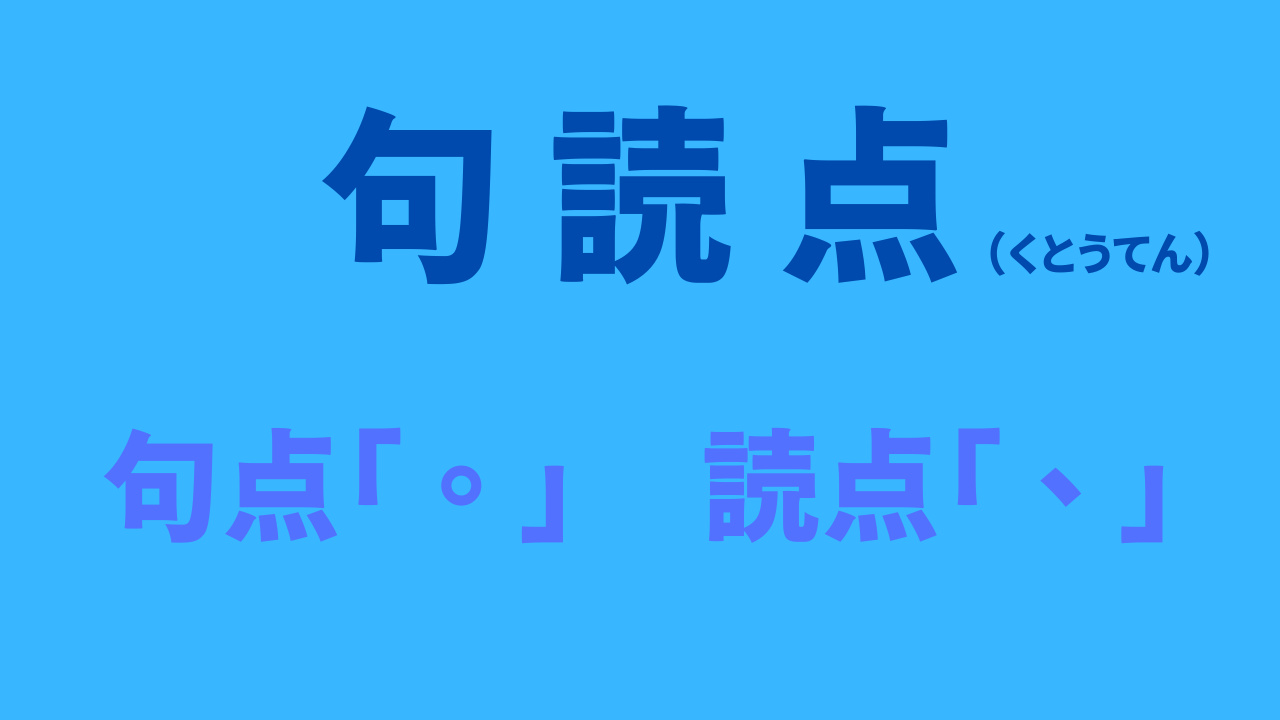- 句点と読点の違いが分からない…
- 句読点をどこに打ったらいいか分からない…
- どうすればもっと読みやすい文章になるんだろう?
- 句読点の使い方の基本を知りたい!
こんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
Webライティングで、読者の心をつかむ文章を書くには、単語や文法だけではなく「句読点」が重要な鍵を握ります。
たった一つの句読点の使い方で文章は劇的に読みやすくなり、読者が最後まで読んでくれる可能性が高まります。
もし句読点の使い方を間違えれば、どんなに素晴らしい記事でも読者はすぐにサイトから離れてしまいます。
本記事では、Webライターが絶対に知っておくべき句読点の使い方、基本ルールを解説します。あなたの文章を劇的に読みやすく変え、読者を引きつける秘訣をお伝えします。
句読点の使い方を学ぶ前に、「書けない」という悩みを根本から解決したい、体系的にWebライティングを学びたい方は、まずこちらの記事をご覧ください。
▶︎ 「【完全保存版】書けない悩みを解決!Webライティングの教科書」

現在会社に勤めながら副業でWebライターをしています。会社では雑誌の編集を担当しており原稿を依頼する側ですが、自宅ではWebライターとして仕事を受けています。
句読点とは?文章の読みやすさを左右する重要な要素

句読点とは何ですか?

句点が「。」で、読点は「、」で合わせて句読点です。
句読点(くとうてん)とは、文章の区切りを明確にし、読みやすさを向上させる重要な要素です。具体的には、句点(くてん)「。」と読点(とうてん)「、」の二つがあります。
句点「。」は文章の末尾に使われ、読点は「、」は文中で使われます。句点と読点でそれぞれの役割があり、正しく理解することが重要です。
| 句読点 | 役 割 |
|---|---|
| 句点(くてん) 「。」 | ①文章の終わりを示す ⇒ 話が一段落したことを知らせます。 ②読者に休息を与える ⇒ 一文ずつ区切ることで読みやすくなります。 |
| 読点(とうてん) 「、」 | ①意味のまとまりを区切る ⇒ 息継ぎのようなものです。 ②誤解を防ぐ ⇒ 読点を打つことで文章の意味を伝えられます。 ③リズムを整える ⇒ 読みやすいリズムを作ってくれます。 |
句点「。」の適切な使い方と基本ルール
はじめに、句点「。」の適切な使い方と基本ルールを解説します。
特にWebライティングでは、一文が長すぎると読みにくくなるため、適切な位置で句点を使いましょう。
1~5の順で解説しますのでご覧ください!
- 一文あたりの「文字数」と句点の位置
- 「一文一義」を意識して句点を配置
- 句点を入れすぎない
- 間違いやすい句点の使い方
- Webライティングにおける句点の使い方!
一文あたりの「文字数」と句点の位置
句点「。」は文章の終わりを示し、読者に一息つくタイミング・休息を与えます。
それでは、一文あたりの文字数は何文字にしたいいのでしょうか?
一文の文字数は、多くても約60文字としましょう。約60文字以内に1回句点が入ることになります。
もし60文字を超えるような文章であれば、以下のように、二つの文章に分けることを検討しましょう!
【NG例】
昨日、会社の昼休みにランチに出かけましたが、目当ての店が混んでいたため別の店を探したものの、5軒回ってどこも満席だったので、結局あきらめてコンビニ弁当を買って戻りました。
△ 86文字
【良い例】
昨日、会社の昼休みにランチに出かけましたが、目当ての店が混んでいたため別の店を探しました。しかし、5軒回ってもどこも満席だったので、結局あきらめてコンビニ弁当を買って会社に戻りました。
○ 45文字 47文字
⇒ NG例では86文字だったものを二つに分割し、45文字、47文字に修正しました。
一文の長さは、多くとも約60文字にしましょう!原則であり、絶対ではありません。
「一文一義」を意識して句点を配置
句点の使い方一つで、読者にとって読みやすい文章になるかどうかが変わります。
「一文一義」(一つの文に一つの意味)を意識して句点を配置することで、より伝わりやすい文章ができあがります。
一文に複数の情報を詰め込むと、読者が混乱して分かりにくくなります。読者にとって分かりにくい文章の場合、サイトからの離脱につながります。
もし一文二義(一つの文に二つの意味)の場合には、以下のように、二つの文章に分けることを検討しましょう!
【NG例】
このセミナーは初心者にもとてもわかりやすく、実践的な内容も含まれていて、学びながら実践できるのが特徴です。
△ 一文二義
【良い例】
このセミナーは初心者にもとてもわかりやすい内容です。実践的な情報も含まれており、学びながら実践できるのが特徴です。
○ 一文一義
⇒ 文章を分けることで、一文ごとに一つの主題(文章が何を述べているか示すもの)を持たせ、読みやすくしました。
【NG例】も内容的に間違いではありません。「一文一義」を意識して分割すると、伝えたいことが整理されてより伝わりやすくなります。
「一文一義」を意識して句点を配置しましょう!
句点を入れすぎない
文章は「60文字以内」で「一文一義」を意識するあまり、句点を多用しすぎても良くありません。
逆に文章が途切れすぎてしまい、不自然で読者にとって読みづらくなってしまいます。
【NG例】
この映画は面白い。とても感動した。ストーリーが良い。映像も綺麗だった。おすすめしたい。
【良い例】
この映画はとても面白く、感動的でした。ストーリーが良く、映像も綺麗だったのでおすすめです。
⇒ 短すぎる文を繋げてリズムよくします。句点の代わりに読点を使って、適度な長さに調整しました。
間違いやすい句点の使い方
句点の位置を間違って打っていることがあります。間違い例を解説します。
原則、かぎかっこの中に句点は打たない
【NG例】
彼は「Webライターになりたい。」と言った。
【良い例】
彼は「Webライターになりたい」と言った。
⇒ 原則、かぎかっこの中の文章に句点は打ちません。
※かぎかっこ「」は文章の中で、「発言」「引用」「強調」する際に使います。
かぎかっこの中に更にかっこを使う場合は、二重かぎかっこ『』を使いましょう。
かぎかっこ内に二つの文章がある場合、一文目の文末にのみ句点
かぎかっこ内に文章が一つだけとは限りません。もし二つ以上の文章がある場合は、一文目の文末に句点を打ち、二文目には句点を打ちません。
【NG例】
彼は「Webライターになりたい。稼ぎたい。」と言った。
【良い例】
彼は「Webライターになりたい。稼ぎたい」と言った。
主語のあと述語が省略されてかぎかっこの文章、更に文章が続くときは句点を打つ
主語のあと述語が省略され、かぎかっこの文章、その後更に文章が続くときは、かぎかっこの後ろに句点を打ちます。
【NG例】
友達が「あなたならWebライターになれる」そのひと言で、やる気がでた。
【良い例】
友達が「あなたならWebライターになれる」。そのひと言で、やる気がでた。
文末が「!」や「?」で終るときは句点を打たない
文章には「!」や「?」で終ることがあります。その場合には句点を打ちません。
【NG例】
私はWebライターになりたい!。
【良い例】
私はWebライターになりたい!
【NG例】
あなたはWebライターになりたいの?。
【良い例】
あなたはWebライターになりたいの?
丸かっこの中の文章には句点を打たない
丸かっこの中に文章を書く場合には、句点を打ちません。
【NG例】
(ライティングの本を読みましょう。)
【良い例】
(ライティングの本を読みましょう)
丸かっこが文末にある場合は句点を打つ
丸かっこ内の内容が、前の文章の部分的な注釈の場合には句点を打ちます。
【NG例】
彼はWebライター(ウェブサイト上の文章を書く人)
【良い例】
彼はWebライター(ウェブサイト上の文章を書く人)。
Webライティングにおいて読みやすくする句点の使い方!
Webライティングでは、サイトから読者の離脱を防ぐために「読みやすい文章」にするのが基本です。
特にスマホでの見やすさを考慮して、以下の二つを意識しよう!
≫改行を意識しましょう。1~2文ごとに改行
≫箇条書きを活用しましょう(長い説明はリスト化)
※三つ以上列挙する際には箇条書きを活用
【NG例】(スマホで読みづらい)
この商品は高品質で耐久性もあり、デザインも優れているため、多くのユーザーに支持されています。さらに、コストパフォーマンスも良く、初心者から上級者まで満足できる仕様になっています。
【良い例】(スマホで読みやすい)
この商品は多くのユーザーに支持されています。
・高品質で耐久性がある
・デザインが優れている
・コストパフォーマンスが良い
初心者から上級者まで満足できる仕様です。
読点(、)の適切な使い方と基本ルール

読点ってどこで打てばいいの?

読点には使い方のルールがあるので解説します!
読点(、)は文の流れを整え、読者が文章を読みやすくします。しかし、読点を入れる位置によっては、意味が変わるので、注意が必要です。
そのため、読点は適切な位置に入れることが大切です。本章では、読点の基本ルールや、適切な配置方法について解説します。
1~10の順で解説しますのでご覧ください!
- 主語と述語の間に原則読点は打たない
- 長い主語の後には読点を打つ
- 文節の切れ目に読点を打つ
- 対等な語句を並べる場合には読点を打つ
- 読点を打ち過ぎない
- 目的語と動詞の間に読点を打たない
- 接続詞の後に必ず読点を打つ必要はない
- 逆説の接続詞・助詞の後には読点を打つ
- 修飾語と被修飾語の間に読点を打たない
- 引用する際「と」の前に読点を打つ
主語と述語の間に原則読点は打たない
修飾語のない主語と述語から成る短い文章は、原則読点で区切らずに書きます。主語と述語の間に読点を打つと、文章が不自然になります。
【NG例】
彼は、書くことが好きです。
【良い例】
彼は書くことが好きです。
⇒ 修飾語のない主語と述語だけで構成された文は、基本的に読点を使わずに書きましょう。
長い主語の後には読点を打つ
長い主語の後には、主語と述語の関係をはっきりさせるために、読点を打ちましょう。
【NG例】
最近サラリーマンにとても人気のある副業はWebライターです。
【良い例】
最近サラリーマンにとても人気のある副業は、Webライターです。
⇒ 主語が長い場合は、主語と述語の関係を明確にするために、読点を打ちましょう。
文節の切れ目に読点を打つ
文節の切れ目に読点を打つことは、ライティングの基本です。文節の切れ目を確認するには、音読することが重要です。
大きい声が出せない場合には、ボソボソとした声でも結構ですので、音読して文節の切れ目を確かめよう。
音読して息継ぎするところに読点を打ちますが、人によって入れる位置は変わるかもしてません。それは許容範囲です。
【NG例】
私は副業で稼ぐためにWebライターを目指して現在ライティングスキルを磨いています。
【良い例】
私は副業で稼ぐために、Webライターを目指して現在ライティングスキルを磨いています。
⇒ NG例も意味は通じますし、間違いではありません。ただ、少し読みにくく感じます。「副業で稼ぐために」と「Webライターを目指して」の間で息をつくために、読点を打つことで読みやすく改善されました。
対等な語句を並べる場合には読点を打つ
対等な語句を並べる場合には読点を打つことで、意味を理解しやすくなります。
【NG例】
サッカーテニスバスケットボールが好きです。
【良い例】
サッカー、テニス、バスケットボールが好きです。
⇒ 対等な語句は、カタカナだけではなく、漢字もひらがなも同じです。
読点を打ち過ぎない
短すぎる文に過剰に読点を入れると、読みにくくなるので注意しましょう!
【NG例】
私は、今日、友達と、飲みに、行きます。
【良い例】
私は今日、友達と飲みに行きます。
⇒ 今日と友達の間のみ読点を一つ打って、漢字の読み間違いを防ぎます。適切に読点を修正すると読みやすくなりましたね。
目的語と動詞の間に読点を打たない
文章の中で、目的語と動詞の間には読点を打たないようにしましょう。「目的語」とは動作の対象となる名詞(人・物・事)」のことです。
【NG例】
「私は記事を、書きました。」
【良い例】
「私は記事を書きました。」
⇒ 目的語「記事」と、動詞「書く」の間に読点を打つと、文章の流れも悪く不自然です。文章も短いので読点は不要です。
接続詞の後に必ず読点を打つ必要はない
Webライターの書籍でも意見が分かれますが、接続詞の後に必ず読点を打つ必要はありません。例えば「そして」「また」「なお」などの接続詞の直後に、必ず読点を打つ必要はありません。
【NG例】
そして、私はWebライターになりました。
【良い例】
そして私はWebライターになりました。
⇒ 文章の流れがスムーズなら、接続詞の直後に読点は不要な場合があります。
※そもそも接続詞がなくても意味が通じる場合は、削ることを検討しましょう。
具体的には「それで」「そして」「したがって」「なお」「また」などがあります。
逆説の接続詞・助詞の後には読点を打つ
逆説の接続詞・助詞の後には読点を打ちましょう。
逆説の接続詞は「しかし」「しかしながら」「ところが」「けれども」など、逆説の接続助詞は「が」があります。
【NG例】
Webライターは魅力的な職業です。しかし誰もが簡単に稼げるほど甘い職業ではありません。
【良い例】
Webライターは魅力的な職業です。しかし、誰もが簡単に稼げるほど甘い職業ではありません。
⇒ NG例でも意味は通じますし間違いではありません。「しかし」の後に読点を入れることで、文の切れ目がはっきりして、読みやすさが増します。
また「誰もが簡単に稼げるほど甘い職業ではありません」という部分を強調する効果もあります。
【NG例】
Webライターは魅力的な職業だがなるのは決して簡単ではない。
【良い例】
Webライターは魅力的な職業だが、なるのは決して簡単ではない。
⇒ 逆説の接続助詞の直後にも読点を打ちましょう。
修飾語と被修飾語の間に読点を打たない
修飾語と、その説明を受ける被修飾語の間には、読点を打たないようにしよう。修飾語と被修飾語の間に読点を入れると、不自然な意味にとられることがあります。
※修飾語は、主語や述語、ほかの修飾語などを詳しく説明する単語です(形容詞・副詞など)。
※被修飾語は、修飾語によって修飾される単語です。
【NG例】
この、美しい写真を見てください。
【良い例】
この美しい写真を見てください。
⇒ 修飾語と被修飾語は、なるべく切り離さないようにしましょう。
引用する際「と」の前に読点を打つ
他人の言葉を引用する際「と」の前に読点を打つと、引用した部分が明確になります。文法的には読点を打たなくてもまったく問題ありません。
【NG例】
Webライターは自分のスキルアップになると編集者が言いました。
【良い例】
Webライターは自分のスキルアップになる、と編集者が言いました。
⇒ 読点より左側は引用部分だと一目瞭然です。
まとめ
句読点を正しく使うだけで、あなたの文章は驚くほど読みやすくなります。句点や読点は、ただの記号ではなく、読み手にストレスを与えず、メッセージを正確に届けるための大切な要素です。
本記事では、Webライターが必ず知っておきたい句読点の基本ルールをご紹介しました。
句点(「。」)は、約60文字を目安に打つ
読点(「、」)は、文節の切れ目や、意味の区切りで適切に入れる
このルールを意識するだけで、文章の印象は格段に良くなります。読者にとって、読みやすく伝わりやすい文章が書けるようになるでしょう。
早速今日から、句読点を意識したライティングを始めましょう。
「もっと体系的にWebライティングを学びたい」「書くことに悩んでいて、具体的な解決策が欲しい」そんな方は、こちらの記事もぜひ参考にしてみてください。
▶︎ 「【完全保存版】書けない悩みを解決!Webライティングの教科書」